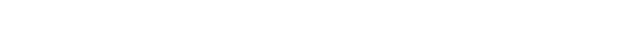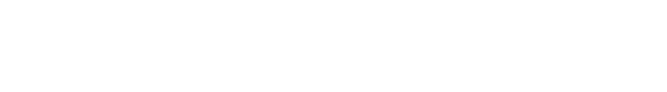お墓や供養についての相談Q&A
Q&A
6つのご相談について、長福寺住職がお答えします。
質問①「永代供養をお願いしたい」
質問②「墓じまいをして樹木葬にしたい」
質問③「墓地を継承する人がいない」
質問④「墓地の維持管理が難しい」
質問⑤「子供に迷惑をかけたくないので墓じまいをしたい」
質問⑥「離檀をしたい」
質問①:「永代供養をお願いしたい」
回答:「永代供養は最終的に無縁仏※①として無縁墓※②に合祀されるのでやめた方がいい」
①一般的な永代供養の相場は「一霊数十万円から数百万円で三十三回忌まで供養する」とHP などで説明しているが将来的には無縁墓に合祀する
→一霊数万円の永代供養墓は無縁墓に埋葬
②霊園は会社経営のため永続的な保証がない
→20~30年以内には少子化により経営が難しくなる霊園がでてくる(宗教法人の認可の元で霊園経営をしているが経営は会社であり、お寺は介入できなくなる可能性がある)
→霊園が倒産すると遺骨管理者が不在となり、遺骨が取り出せなくなる可能性がある ※北海道白鳳寺の例
③長福寺の永代供養墓は合祀なので檀家に奨励していない
→親族の墓への合祀をすすめる
→墓は誰でも継承できる(施主が墓の権利を継承することをお寺が承認すれば誰でも可能)
→少子化の日本では、今後は「一軒で墓一基」ではなく「数軒で墓一基」が合理的
→お寺に墓をもつことは永続的に管理が可能(長福寺は1300年)
→今後20年で現在7万ヶ寺の半数は住職不在のお寺になる可能性
※①無縁仏・無縁墓は歴史的に孤独死や身元不明のご遺骨を合祀する場所→まとめて遺骨を納める
※②近年、無縁墓を永代供養墓と言い換え霊園・一部のお寺で奨励しだした→経済的な理由

質問②:「墓じまいをして樹木葬にしたい」
回答:「霊園樹木葬はおすすめできない」
①霊園での樹木葬も永続的な保証がない(20~30年以内に難しくなると予測)
→誰も手をつけられない忌み地のような土地になる可能性あり
→霊園での樹木葬を選択するなら、永代供養墓に納めるか散骨した方がいい
②お寺での樹木葬は、今後住職不在になる可能性があるお寺が推奨している場合が多い
→お寺での樹木葬は、永続的に土地を占有する上に、檀家になる可能性が低い
③江戸以前の貧しい時代に遺体をそのまま埋めて自然石を置いただけの簡素な墓地と同義
→墓地を一基作り、親族みんなで埋葬される墓地の方が経済的に合理的

質問③:「墓地を継承する人がいない」
回答:「墓地は親族であれば、だれでも継承できる」
①墓地は個人財産(土地はお寺が永代に貸与)
→施主が認めれば誰でも墓の権利を継承することが可能
②墓地は施主が認めれば誰でも埋葬することが可能
→同じ姓を持つものしか埋葬できないと思い込んでいる方が多い
→ただし、お寺での葬儀が必要(過去帳に記載し永代に渡り供養することで、亡き人の仏徳を高め、家族の安寧を祈る)
→葬儀とは、お釈迦様の弟子である住職を通じて、弟子の証である戒名を授与され、お釈迦様の遺徳を継ぎ仏様として永代に渡り子孫を安寧に導く存在とすること
→俗名葬儀は葬儀ではなくお別れ会(俗名の葬儀に対しての僧侶の読経は無意味)
③少子化の日本では、今後は「一軒で墓一基」ではなく「数軒で墓一基」が主流になると予測できる
→100年先まで安心して埋葬できる場所を選択する必要がある
→霊園は100年先までは、公営のもの以外は存続している可能性は低い
→ある程度の規模のお寺に埋葬することが理想的(今後20年以内に半数は住職不在になる予想)
④親族間仲良くすることが最重要
→存命中に、親族間のコミュニケーションをしっかりとる
→皆で一緒に入れるお墓を持つことが一番経済的に合理的
→自分がどこで安らかに眠ることができるか明確にすることで安心できる
→遺骨に霊魂が宿る考えは普遍的

質問④:「墓地の維持管理が難しい」
回答:「少しの工事で管理は難しくない」
①墓地は草の生えない工事(草が生える場所を石張りにする等)をすれば問題ない
→遠方ならば正月・お盆など年1~2回でもお参りはいいのではないか
②花を生けることが困難
→月命日などにお参りするのが理想的だが、難しければ造花(あまり推奨しないが)を用いるか、お寺にお願いすることも可能

質問⑤:「子供に迷惑をかけたくないので墓じまいをしたい」
回答:「墓じまいとは、先祖の遺骨を粗末に扱うことと同義」
①近年その言葉が定着し、上記のような理由で墓じまいを選択しようとするが、「遺骨を丁寧に祀れない」「永続的にお祀りできない」などのデメリットが発生することを理解していない
→子供と相談をしていない
→親が亡くなった時に埋葬する場所・方法が決定していないと子供の負担が増加する
→「墓じまい」は仏教的な言葉ではなく、霊園関係者が近年生み出した言葉と推測される
→10代遡ると先祖は千霊、20代遡ると百万霊をお墓にお祀りしていることとなる
→「墓じまい」とはすべての先祖を廃棄することと同義であり、本来ならば他に手段が見つからない場合に、否応なく選択せざるを得ないもの
→お墓の管理をする必要がなく、霊園に任せれば楽で安心と思っている傾向があるが、墓地管理にかかわる諸経費は霊園の方が高い場合もあり、しかも永続性は期待できない
→お寺で管理することは面倒ではない
→個人主義化がより顕在化する社会背景などにより日本古来の家制度が崩壊しつつあるが、AIの台頭などを考慮すると、AIで答えることのできない人間の本質的な悩みに対して、より意識が高まると予想

質問⑥:「離檀をしたい」
回答:「信仰心がなかったとしても、お寺の檀家であることは経済的なメリットが高い」
①一般的な葬儀で一番高額なのはホール使用料(20~50万)
→檀家でない場合、俗名葬儀+ホール使用料+永代供養費+諸経費
→以上は一時的な葬儀費用のみで、永続的な亡き人への慰霊費は含まれない
②長福寺の檀家であれば無料で本堂を葬儀に使用可能 布施+諸経費
→お寺の葬儀は、戒名・葬送儀礼・永続的な供養費用を含む
→長福寺の最古の檀家は500年前から朝課(朝のお勤)で供養
→俗名葬儀は儀礼として無意味(15万布施の意味が不明)※質問3の②参照
③お寺のお墓に埋葬する場合は、埋葬費など追加の金銭は発生しない
→霊園などでは樹木葬・永代供養の場合は一霊数十万円で計算する
→お寺に埋葬する場合、年忌後に埋葬
→親族で使うならお墓を持つ方が経済的に有利
④お墓は個人財産
→墓地造成の費用(長福寺永代使用料10~20万、墓地費用60万~200万、墓地管理費無料)
→墓地造成は70万で可能(一基作れば何霊も埋葬が可能で経済的にも合理的)
→墓地を作れない場合は、基礎をなくし墓石のみなら、さらに安くなる
→親族で墓地を継承することが一番合理的
→長福寺が檀家に求めるのは、葬儀法事は長福寺のみで行うことと年一回の護持会費(3500、6200、9000、 12000、 15000円の五段階。各自で選択)
→長福寺は多額の寄付を求める予定はない
→檀家であることの年間最低費用は 3500円のみ(正月・盆等の供養費は任意)
⑤永続的な故人への供養
→長福寺は 1300年の歴史であり、現在の檀家数などから推測するに今後住職不在になる可能性は低い(今後20年以内にお寺の半数は住職不在になる可能性)
→長福寺位牌堂には1万霊をお祀りし、本堂裏山の行者山は古墳時代より死者を埋葬していた、地域の霊山として存続している
→「お墓参り」は日本人の宗教文化として定着しており、この傾向は今後も続くと予想できる(AI時代に個人のアイデンティティとして必要性が増す可能性も予測)
→今後100年、安心して故人を慰霊できる場所を確保したことになる(一族のランドマークとして重要になる可能性)
⑥お寺との付き合い(付け届けなど)
→付け届け・年忌などはすべて施主の判断でお勤めするもの
→正月お盆には受付を設け、付け届けの受付をするが、お布施を頂いた場合にはご供養をして返礼の品をお渡しする
→返礼の品
正月・・・干支陶器楊枝入・大般若お守・祈祷証
お盆・・・長福寺新聞・粗品・うちわ・菓子(ご祈祷済)・お盆のしおり
⑦お寺からの授与品
正月・・・大般若お札(1年の安寧を本尊様に祈願したお札)・仏教冊子・長福寺新聞・宝暦・福箸(輪島塗)
⑧将来的に誰も墓地を継承する人がいなくなった場合
→最後の一人がまとめて永代供養墓に収めるのが経済的・宗教的にも合理的
→一霊数十万円ずつ永代供養墓や樹木葬にするのは不合理

檀家とは、お寺(御本尊様)が持つご利益を各家の仏壇を通じて家族全体を仏の加護で守護し防衛すると共に、ご先祖様を御本尊様の加護の元、未来永劫に渡り仏様として祀り続け、より徳の高い仏様として生かし続けることをお寺が保証するシステムです。
墓地や入檀に関するご相談はお問い合わせください。
安里山 長福寺
〒436-0111 静岡県掛川市本郷1389-1
電話:0537-26-0041(電話受付時間9時~16時)