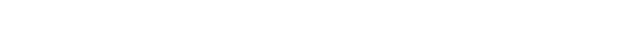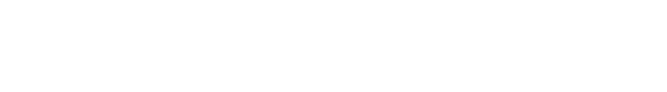伝説「空を飛んだ釣鐘」
The Legend of "The Flying Temple Bell"
修験道の開祖、役行者ゆかりの寺長福寺の鐘にまつわる不思議な伝承
釣鐘伝説
その昔、長福寺の和尚が碁を打っていると、
みすぼらしい身なりの怪しげな山伏か行者のような男が現れた。その男が路銀(お金)を乞うてきたので、和尚は「金は無い、この寺にあるのは鐘だけだ」と答えた。
すると山伏は「では鐘をもらっていいか?」と問うたので 和尚は、「持っていけるものなら持っていくといい」と返答すると「それはありがたい」と、謎の行者はふわりと浮き上がり重い鐘をもって西の空に飛び去ったという。
この行者こそが、修験道の開祖と呼ばれる「役小角・役の行者」であり、今でも修験道の聖地である奈良県の大峰山には長福寺と刻まれた梵鐘が残され、国重要文化財とされている。
それ以来、長福寺では鐘を鋳造しても割れたり焼け落ちたりし、ついぞそれ以来、世にも珍しい鐘の無い寺として、 鐘の代わりに6尺の大太鼓を打つことになったという。
この長福寺に残る不思議な伝承は「遠江古跡図絵(1803年)」の他、多くの記述が残っている。

現在でも大峰山には、長福寺と刻銘の残る鐘があり、その鐘をかけた岩なども名所として残っている。
 銘に刻まれた年、天慶七年(944年)の時代にも、遠州の長福寺という寺は、奈良県をはじめ西国にも知られた寺であったと思われる。
銘に刻まれた年、天慶七年(944年)の時代にも、遠州の長福寺という寺は、奈良県をはじめ西国にも知られた寺であったと思われる。

藤長庚 編『遠江古蹟圖會3巻』 [写] 国立国会図書館デジタルコレクション
https://dl.ndl.go.jp/pid/2538219
千年間も伝えられた伝承ゆえに、多くのパターンが存在するが、その多くは住職と旅の山伏との会話があり、金を欲した山伏に長福寺の住職が鐘でよいなら、と答えたところ釣鐘を持ち飛び去り、奈良県の大峰山に運ばれた。その謎の山伏は役行者であった。それ以来長福寺では鐘を作るが鳴らなかったり焼け落ちたりしたので、ついぞこの寺には鐘がなく、いまでは鐘の代わりに6尺の大太鼓を持つというものである。https://dl.ndl.go.jp/pid/2538219
現在でも大峰山には、長福寺と刻銘の残る鐘があり、その鐘をかけた岩なども名所として残っている。

鐘の掛かった松があった岩場は「鐘掛岩」として大峰山の修行場となっている。
長福寺の鐘にまつわる数多くの伝承
大峰山に残された、長福寺の鐘にまつわるエピソードは数多く存在する。長福寺の鐘
鐘掛け岩・鐘掛け松
油こぼし
など、伝承のパターンも数多く、千年前のエピソードが今も形をかえて数多くの書籍や伝承に残されている。
また、静岡県旧豊岡村の獅子が鼻公園には、飛び去った役行者が鐘をかけて休んだといわれる鐘掛岩が伝えられている。
以下に長福寺の鐘についての詳細や長福寺の鐘にまつわる数多くの伝承を紹介する。
| 大峰山に伝わる長福寺の鐘 |
奈良県、大峰山寺の本堂内には「遠江國佐野郡原田郷 長福寺鐘 天慶七年六月二日」という後刻銘のある梵鐘(国指定重要文化財)が現存する。総高119.7cm 、径66.8cm、重量100貫(375kg)
「天慶7年(944年:平安時代中期)」の銘は追刻で、梵鐘自体は奈良時代の作。
奈良時代に鋳造されたと確認されている日本最古の釣鐘(16口)のひとつである。

[聆涛閣集古帖]鐘銘 国立歴史民俗博物館
一五、金峯山寺大峯鐘(拓、天慶七年六月二日、遠江国佐野郡原田鄉長福寺)

松平定信 編『集古十種』鐘銘之部 上,郁文舎,明36-38.
国立国会図書館デジタルコレクション
https://dl.ndl.go.jp/pid/849529
https://dl.ndl.go.jp/pid/849529
| 寺記に云く |
『遠江国佐野郡原田郷安里山長福寺略縁起』明和3年(1766)版より伝え聞く、本朝に龍宮より下る所の鐘三口あり、是その一つなり、長暦元年(1037)一日山伏来る。
その骨相凡ならず、止宿せしむ、終夜論談旧識の如し。則ち修力の功験に及ぶ、山伏金剛杖を以て楼上の鐘を指て云く、持去ることを許さんや。住僧許諾す。
終に山伏鐘を提て空中を飛行し去ると。誠にその鐘大峰山上に止む・・・その山伏は役行者(役小角)の化身ならんや。その因縁により大峰山寺より役行者尊像を勧請し、裏山山頂に一宇を建立しまつる。(秘仏、33年目に大開扉あり)この空を飛んだ釣鐘は現在奈良県吉野郡の修験道の根本道場、大峰山頂(1719米)の大峰山寺に現存す。

『遠江国佐野郡原田郷安里山長福寺略縁起』
| 長福寺のふしぎな鐘 ~空を飛んだ釣鐘伝説~ |
むかしむかしのこと 長福寺のつり鐘は、遠州でも他にないほどみごとなものでした。ある日、旅のお坊さんが一人長福寺をたずねてきました。
「わたしは、これから大和 (奈良県) の国までいくのですが、お金に困っています。少しいただけませんか」と言いました。その時、村の人と碁を打っていた和尚さんは「だめだ、お金なんて一文もないよ。“かね”とつくものはあのつり鐘くらいのものだ。あれでよければ持って行きなさい。」と答えました。
長福寺の釣鐘は、大きくて一人や二人ではびくとも動かないので和尚さんは、からかって言ったのでした。ところが旅のお坊さんは、「ほう、あのつり鐘ならいいのですね。」そう言って目を光らせました。
「ああ、いいとも」と答えると旅のお坊さんは、釣鐘を杖 (金剛杖)にさし「では、おしょう、もらっていくぞ」 と、ふわりとかつぎ上げ、西の方にむかって飛んでいってしまいました。
そうして、その夜の事。「役行者尊」という尊い仏様をまつる大和の国の大峰山では、急に大風と大雨が起こり、 地の底からゆれるような、ものすごい山鳴りがしました。
そして夜があけてみると、はるか先の切り立ったような岩山の上の大松に大きな鐘がかかっているのが見えました。村人が苦心してそのつり鐘をみると『遠江国 佐野群原田郷 長福寺鐘 天慶七年六月二日』(天慶七年とは 西暦944年)とほりつけてありました。
やがてこの事は長福寺まで伝えられ、大峰山から役行者尊の霊をお迎えしておまつりする事にしました。
その後、長福寺では何度も釣鐘を作りましたが、どれもうまくいかず、ついに釣鐘を置くことはあきらめました。
| 釣鐘のない寺 |
鐘が大峰山に飛んでいってしまって以降、長福寺には釣鐘がありません。寺伝『遠江国佐野郡原田郷安里山長福寺略縁起』明和3年(1766年)には、
「鐘が持ち去られた後、3度鋳造しようとするがうまくいかなかった。その後、近隣の修験者が祈願し、ようやく鐘を備えることができたが、その鐘の音は村の外に響くことはなかった。寛保3年(1741)8月、出火し鐘は裂けて地に落ちる。当山において鋳鐘は戒めるべきである。」と、鐘のない理由が書かれています。
| 遠州行者太鼓 |
釣鐘にかわって大きな音を出す、六尺の桶胴太鼓です。

その他12個の大中小の太鼓による組太鼓があり、役行者尊大開帳等の祭典にて奉納演奏されます。

正徳3年(1713)『和漢三才図会』
享保9年(1724)『金峯山古今雑記』
享保14年(1729)『諸州採薬記』
享保21年(1736)『輿地通史』
明和3年(1766)『遠江国佐野郡原田郷安里山長福寺略縁起』(版木)
安永10年(1781)『長福寺鐘之縁起』(二枚組、版木)
寛政3年(1791)『大和名所図会』
寛政11年(1799)『遠江風土記伝 酉巻第十一 佐野』
文化2年(1805)『掛川誌稿』
享和3年(1803)『大峯細見記』
享和3年(1803)『遠江古蹟図会』
天保5年(1834)『遠淡海地誌』
文政4年-天保12年(1821-1841年)『甲子夜話続篇 巻之十』
最も古いとされるのが『和州旧跡幽考』延宝9年(1681)にある、
「鐘あり鐘楼もなく堂の緑にすえ置きたり其の銘曰 遠江國佐野郡原田庄 長福寺天慶六年七月二日と云々 延宝七年迄凡七百三十七年歟」という記述です。 年月がやや違いますが、17世紀後半に、鐘は大峰山寺本堂縁に据えられ、銘文がすでに刻まれていたことが確認できます。
次に古い『和漢三才図会』正徳3年(1713)では、「役行者が長福寺で施を乞い、鐘の龍頭に錫杖を貫き、高下駄を履いて鐘を担げて持ち去り、鐘掛松に掛けた」という今に伝わる伝承に近い内容となっています。
これ以降の文献では細部の違いはありますが、同様のエピソードが紹介されています。
《参考文献》
森下恵介「大峰山寺鐘小考」『王権と武器と信仰』同成社2008年
山本義孝『遠江の役行者信仰~「建立150年前浜行者堂と役行者信仰展」からの知見~』(平成27年度・静岡県博物館協会研究紀要第39号)

| 「往のう」と響く鐘 |
大峰山寺では、長福寺銘の入った鐘は、撞くと「往のう(帰りたい)」と響くため、撞木はなく撞かないと伝わります。| 長福寺の鐘(銘文、伝説)についての記述がある文献 |
延宝9年(1681)『和州旧跡幽考』正徳3年(1713)『和漢三才図会』
享保9年(1724)『金峯山古今雑記』
享保14年(1729)『諸州採薬記』
享保21年(1736)『輿地通史』
明和3年(1766)『遠江国佐野郡原田郷安里山長福寺略縁起』(版木)
安永10年(1781)『長福寺鐘之縁起』(二枚組、版木)
寛政3年(1791)『大和名所図会』
寛政11年(1799)『遠江風土記伝 酉巻第十一 佐野』
文化2年(1805)『掛川誌稿』
享和3年(1803)『大峯細見記』
享和3年(1803)『遠江古蹟図会』
天保5年(1834)『遠淡海地誌』
文政4年-天保12年(1821-1841年)『甲子夜話続篇 巻之十』
最も古いとされるのが『和州旧跡幽考』延宝9年(1681)にある、
「鐘あり鐘楼もなく堂の緑にすえ置きたり其の銘曰 遠江國佐野郡原田庄 長福寺天慶六年七月二日と云々 延宝七年迄凡七百三十七年歟」という記述です。 年月がやや違いますが、17世紀後半に、鐘は大峰山寺本堂縁に据えられ、銘文がすでに刻まれていたことが確認できます。
次に古い『和漢三才図会』正徳3年(1713)では、「役行者が長福寺で施を乞い、鐘の龍頭に錫杖を貫き、高下駄を履いて鐘を担げて持ち去り、鐘掛松に掛けた」という今に伝わる伝承に近い内容となっています。
これ以降の文献では細部の違いはありますが、同様のエピソードが紹介されています。
《参考文献》
森下恵介「大峰山寺鐘小考」『王権と武器と信仰』同成社2008年
山本義孝『遠江の役行者信仰~「建立150年前浜行者堂と役行者信仰展」からの知見~』(平成27年度・静岡県博物館協会研究紀要第39号)